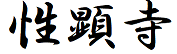家のお仏壇どのようにお世話すればいいのだろう?なんとなくお坊さん来たら一緒にお参りしているけど、どんな意味があるのだろう?普段悩まれていることはありませんか?
ここでは、代表的な家庭での仏事を取り上げ、その意義等をご説明させていただきます。
日常のお給仕
仏祖への敬いの心から、お仏壇のお世話をすることをお給仕といいます。お花を供え(供華)、香を供え(供香)、お仏飯を供え(供飯)、餅、菓子、果物などを供えます(供物)。また、お仏壇の掃除も大切なお給仕です。お仏壇は物置ではないので、できるだけ余計なものは置かずに、清潔に保っておきたいものです。
お仏壇のお飾りの仕方はこちら→荘厳図ページへ
家庭で行う仏事
- 葬儀
- 詳しくはこちら→葬儀ページへ
- お取越し報恩講
- 各家庭で勤められる「報恩講」のことをいいます。報恩講とは宗祖親鸞聖人のご法事です。「お取越し」という方が耳になじみがあるかもしれませんが、「お取越し」というのは、先んじて勤めるという意で、御本山の報恩講よりも先に勤め、共に御本山の御正忌報恩講にお参りをしましょうというのが「お取越し」の趣旨です。「お取越し」を勤めることは真宗門徒のたしなみとして、代々大切に受け継がれています。
- 年忌(年回)法要
- 故人を縁として遇わせていただく仏事のことをいいます。一般に法事ともいいます。地域差がありますが、亡くなった翌年が「一周忌」、翌々年が「三回忌」、以後「七回忌」、「一三回忌」、「一七回忌」、「二三回忌」、「二七回忌」、「三三回忌」、「三七回忌」、「四三回忌」、「四七回忌」、「五〇回忌」までご案内をさせていただています。
- 祥月法要
- 年忌法要がない年の当たり月の命日に勤めます。
- 月忌法要(定飯、常飯、逮夜参り)
- 毎月の月命日に勤めます。
- 入仏・遷仏法要
- 新たに御本尊(お仏壇)をお迎えしたときに入仏法要を勤めます。また、お仏壇のお洗濯や、引っ越し等で、御本尊にご移動していただかなくてはならないときは遷仏法要を勤めます。俗に「お性入れ」「お性抜き」と呼ばれますが、お勤めすることによって何かを出し入れするわけではなく、あくまでも敬うべき対象を扱わせていただくという気持ちから勤めます。また、主にお墓等で勤める建碑法要も、入仏・遷仏法要と同じ趣旨です。
- 納骨・遷骨法要
- 納骨堂へのお納骨はこちら→無量寿堂ページへ
- お墓や、納骨堂にご遺骨納める時に納骨法要を勤めます。またご遺骨を移動しなければならないときは遷骨法要を勤めます。
- 盂蘭盆会
- 一般にいう「お盆」のことです。私たちの「お盆参り」はご先祖への報恩の思いから、私自身が仏法を聞かせていただき、この身を慶ばせていただくご縁です。それがまたご先祖への恩に報いることになっていくのでしょう。
- 初逮夜(おはじまり)
- 一年の初めの「逮夜参り」。かつて交通機関が発達していなかった時代は、寺から遠方の地域の家庭に定期的にお参りに伺うのが困難でありました。そのため、毎月の月命日(逮夜参り)は直近のお寺に依頼し、一年の初めだけ師匠寺から「逮夜参り」に伺っていた習慣が受け継がれているのでしょう。
その他ご相談があれば性顕寺までお問い合わせ下さい。